要約(冒頭)
セキュリティトークン(Security Token, 以下 ST)は「ブロックチェーン等の技術で有価証券の権利を表示・移転するデジタル化された証券」です。日本では金融商品取引法の改正(2020年施行)の整備を受け、実案件が次々に出現しています。個人向けの社債型トークンから大規模な不動産を裏付けとした不動産STまで、発行主体・規模・スキームは多様化しています。本記事では主要な国内事例を整理し、プラットフォーム・法制度・メリット・リスクを踏まえた将来展望まで、実務寄りに解説します。
1. 「国内事例」:代表的な発行案件と特徴
SBI証券:個人向け公募の社債型ST(2021)
SBI証券は国内で初めて(※一般投資家向け)社債をセキュリティトークンとして発行しました。発行額は小規模に抑えられ、投資単位が比較的小さく(少額投資の入口として設計)ブロックチェーン基盤には国産コンソーシアム基盤(例:BOOSTRYやibet for Finに準じたスキーム)が用いられた点が特徴です。これにより「デジタル化×既存証券の組合せ」の先行事例となりました。
ケネディクス(不動産ST):リバーシティ月島(2023)
ケネディクスの不動産を裏付けとした「不動産リアルティトークン」は、国内でも規模が大きい事例のひとつです。大口物件をトークン化して分配・権利表示を行い、投資家はトークン=受益権のデジタル表現を介して投資します。引受・流通支援に大手証券や信託銀行が関与するケースも増え、オフライン(不動産)とデジタル証券の接続が現実化しています。
三井物産系や野村らの取り扱い(2022〜)
三井物産デジタル・アセットマネジメント等も不動産関連の大型案件を手掛け、野村が仲介/取扱で複数案件を支援するなど、メガプレイヤーの関与が目立ちます。これにより案件スケールの拡大と、既存金融インフラ(銀行、信託、証券)との連携が進んでいます。
2. プラットフォームと実務スキーム(どうやって発行・管理されるか)
- ブロックチェーンの種類:日本ではパーミッション型(参加者限定)のDLTを使うケースが多く、権利移転やKYC/AML管理が法規制に沿って行われる設計が一般的です。
- コンソーシアム基盤:BOOSTRY(野村などが関与)や「ibet for Fin」等、業界コンソーシアムが基盤を提供し、発行・受託・管理といった役割分担を明確化するスキームが用いられています。
- カストディ/保管:秘密鍵管理や受益権保管(信託や保管振替機構の活用)について、従来の「ほふり」等の仕組みをどう接続するかが実務上の重要点です。
3. 規制・ガイドライン(日本の現状)
2020年の金商法改正により、「電子記録移転有価証券表示権利等」として法的取り扱いが明確になりました。金融庁や日本STO協会の議論を通じて、自主規制や監督の枠組みも整備段階にあります。これによって発行は法令準拠で行うことが前提となり、既存金融制度との整合性(投資家保護、情報開示等)が求められます。
4. 比較表(主要国内事例の簡易比較)
| 項目 | SBI証券 (2021) | ケネディクス(不動産ST・2023) | 三井物産系(那須等・2024) | スパークス等(デジタル社債) |
| 資産種類 | 企業社債 | 不動産(マンション) | 不動産(商業施設等) | 事業会社社債(デジタル) |
| 発行年 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 |
| 発行額の目安 | 小規模(約1億円) | 大規模(数十〜百億円台) | 100億円規模 | 10億円前後 |
| 投資対象 | 個人投資家向け公募 | 公募(譲渡制限付) | 公募/私募 | 個人向けの公募引受型 |
| 技術基盤 | コンソーシアム型DLT(BOOSTRY等) | コンソーシアム/プラットフォーム | 同上 | 同上 |
| 流通性 | 限定(プラットフォーム上) | 譲渡制限あり/将来的流通可能性あり | 同上 | 限定流通 |
| 主な関係者 | SBI(発行)・BOOSTRY等 | ケネディクス・野村など(引受/販売支援) | 三井物産デジタルAM・野村等 | スパークス・野村など |
| 特徴 | 個人向けの先行事例 | 国内最大級の不動産ST | 大型商業不動産で拡大 | 事業会社のデジタル債の先例 |
(出典:各社プレスリリース/業界報告の整理)。
5. STOがもたらすメリット(投資家/発行者それぞれ)
発行者側
- 資金調達の多様化(小口化やグローバル投資家の呼び込みがしやすい)。
- 資産の流動化・トークン化によりB/S上の利用価値が向上。
投資家側
- 小口からの参入が可能になり、これまでリテールに回らなかった資産にアクセスできる。
- ブロックチェーンにより権利情報の透明性向上(改ざん耐性等)。
6. リスクと課題
- 流動性の制約:多くの国内案件は当面、譲渡制限付きやプラットフォーム内流通に留まるため、二次市場の流動性は限定的。
- 法制度の不確実性:金融庁の監督や実務の解釈がさらに成熟する必要がある(ガイドラインの蓄積が鍵)。
- 運用・管理のオペレーショナルリスク:カストディ(秘密鍵管理)、KYC/AML、会計処理のルール整備などが課題。
- 投資家保護:情報開示や説明責任のあり方、詐欺的スキーム防止が求められる。
7. 将来性(5年〜10年の見通し)
- 商品幅の拡大:不動産以外(事業投資、インフラ資産、ファンド持分、IP権利等)へのトークン化が進む見込み。
- 二次流通市場の整備:取引所型プラットフォーム(セカンダリー市場)や認可された取引インフラが成熟すれば流動性は改善する可能性が高い。
- 既存金融との融合:信託、受託、証券代行など既存金融インフラとの連携が進むことで、法令・実務の壁が低くなる。
- 国際展開の可能性:国内で磨かれたスキームが国際的な投資家/プラットフォームと接続すれば、クロスボーダー資金調達の選択肢になる。
総じて、「技術だけでなく法制度・インフラ整備・既存金融プレイヤーの参入」が進む段階であり、実需と制度整備が揃えば中長期での拡大が期待できるというのが現実的な見立てです。
8. 実務担当者向けチェックリスト(発行側)
- 金商法との整合性(電子記録移転有価証券の扱い)を弁護士・監査と確認。
- KYC/AML・投資家適合性の設計(個人向けか機関向けかで要件が変わる)。
- カストディ(鍵管理)とバックアップ設計の明確化。
- 流動化/セカンダリーをどの程度想定するか(譲渡制限やプラットフォーム設計)。
- 開示資料(目論見書的な情報)と投資家説明のプロセス整備。
9. まとめ(結論)
日本のSTO市場は「法整備 → 先行実績 → 大手金融の関与 → 規模拡大」という流れをたどりつつあります。SBIの個人向け社債トークンから、ケネディクス等の大型不動産STまで、実案件が示す通り需要は存在し、インフラ整備と規制の安定化が進めば普及は加速するでしょう。ただし現時点では流動性や投資家保護など実務的な課題も多く、発行側・投資側ともに注意深い設計と段階的な展開が必要です。今後のポイントは「セカンダリー市場の成熟」と「既存金融インフラとのスムーズな接続」です。
参考(主要ソース)
- 金融庁/日本STO協会における報告書・資料(セキュリティトークンの定義と法的位置づけ)。
- SBI証券:国内初の一般投資家向けSTO(プレスリリース)。
- 野村ホールディングス/ケネディクス関連の取扱実績(不動産ST 大型案件)。
- SBbit / CoinDesk Japan 等の記事(国内市場の経緯と案件一覧まとめ)。
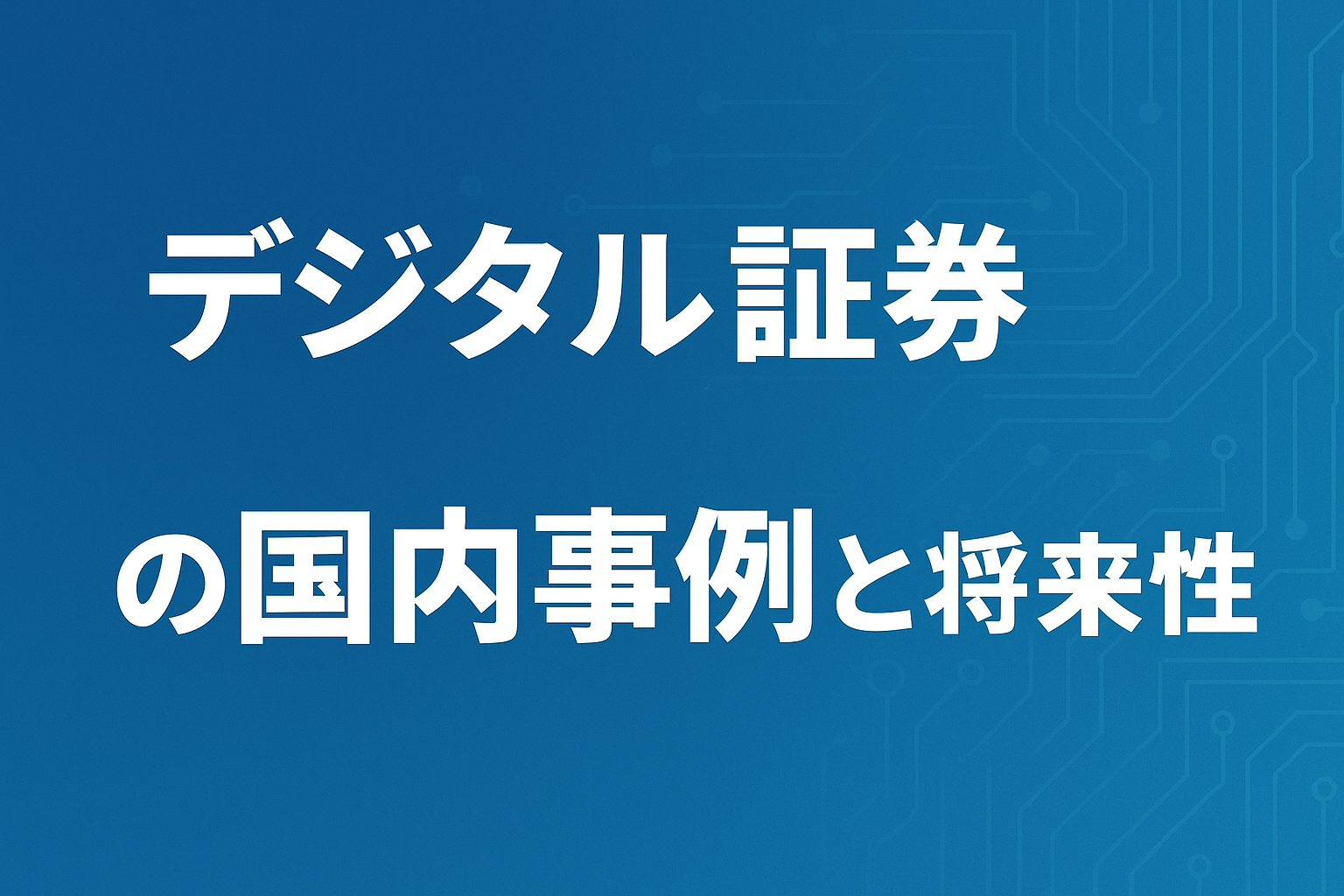
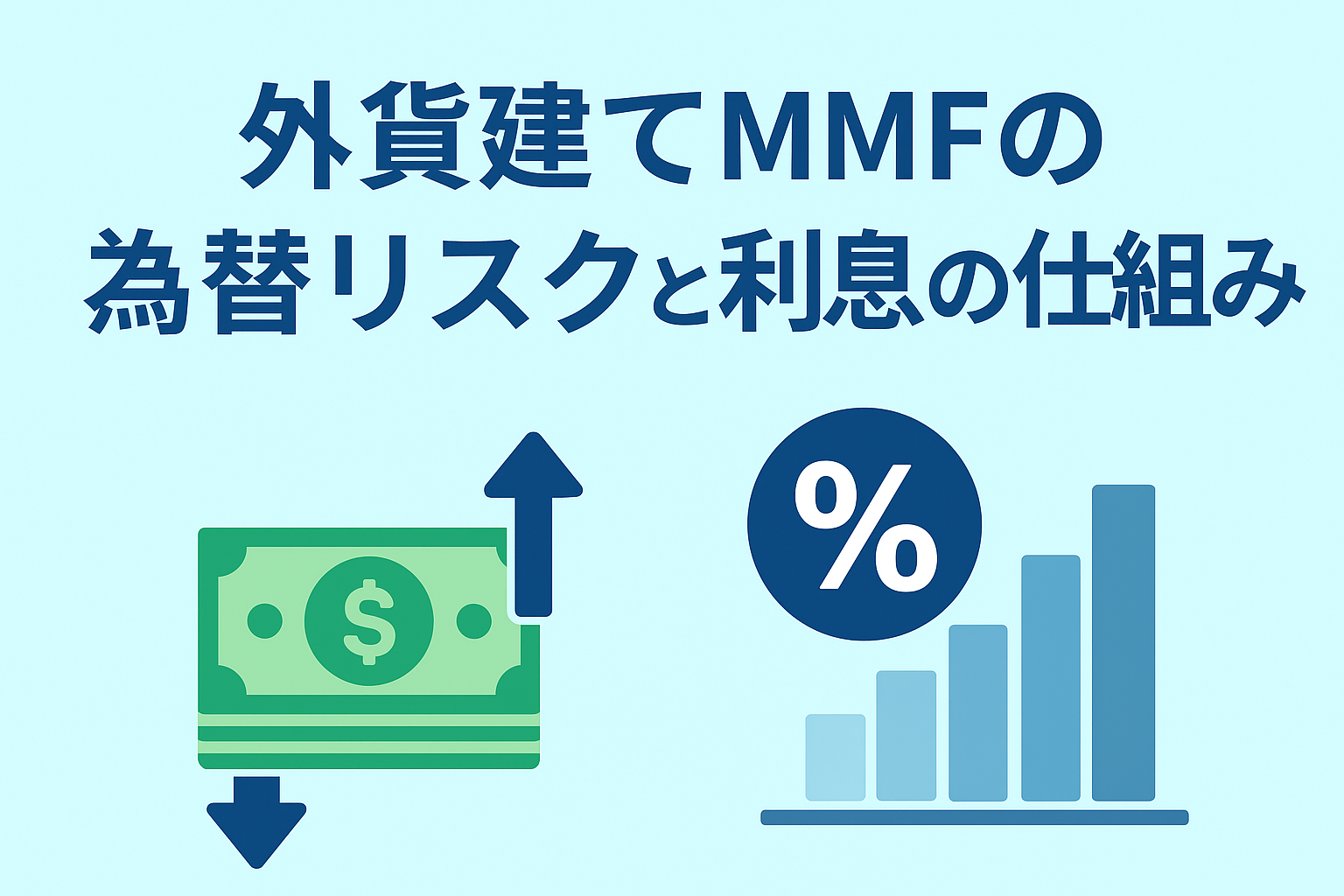

コメント