未公開株(非上場株)を個人が「中古で買う(=既存株主から譲り受ける)」のは、とてもハードルが高い――。この一文に、日本の未公開株セカンダリー市場の実情が凝縮されています。上場株のような取引所・PTSが整備され、指値で気軽に売買……という世界は、少なくとも今の日本では一般投資家にとって現実ではありません。本稿では、制度面・売買の実務・新たな動き・注意点まで、未公開株の“中古市場”のリアルを俯瞰します。
1. なぜ未公開株は自由に売買できないのか(制度の骨格)
日本の非上場会社の多くは、譲渡制限株式を発行しています。これは「株式の譲渡に会社の承認が必要」という定款ルール。会社法は、譲渡制限株式の株主が他人へ売ろうとするとき、会社に承認するか否かの決定を請求できると定め、承認手続き(取締役会等の決議)を要します。したがって、売り手と買い手が合意しても、会社の承認が降りなければ成立しません。加えて、株式の譲渡は**株主名簿に記載(名義書換)**されて初めて会社や第三者に対抗できます。上場株のようにブローカー経由で即日決済…とは行かないのが基本構造です。
この「会社の承認」が挟まる構造は、望まない第三者が株主名簿に入り込むのを防ぐ統治上の合理性がある一方で、市場流動性を大きく制約します。だからこそ、未公開株のセカンダリーは“マーケット”というより個別案件の承認付き私設取引の色合いが濃くなります。
2. 公式な「市場」に見えるが一般投資家は直接買えない場所:TOKYO PRO Market
「東京証券取引所にも未公開寄りの市場がある」としてTOKYO PRO Market(TPM)が挙げられます。しかしTPMは特定投資家(プロ)等に限定された市場で、一般投資家は直接買付ができません(保有している株を売却することは可)。形式基準がなく上場要件が柔軟な分、プロ限定の制度設計です。一般投資家の“中古株の売買の場”と誤解しないよう注意が要ります。
3. 過去の「未公開株の場」はなぜ消えたのか:グリーンシートの終焉
2000年代から2010年代にかけ、**日本証券業協会の「グリーンシート制度」**が、未公開株の情報提供・売買の受皿と目されましたが、2018年に廃止されています。制度的な“公式セカンダリー”が姿を消したことで、未公開株の流通は一段と限定的になりました。
4. それでも流通はゼロではない:どこでどう動いている?
4-1. 株主コミュニティ(JSDAスキーム)を使った限定的な売買
株主コミュニティとは、地域の未上場企業の株式の売買・発行を、参加者限定の枠内で行う仕組みです。近年はオンライン化が進み、FUNDINNO MARKETは「インターネットで未上場株式を売買できる日本初のマーケット」と位置付け、株主コミュニティ制度を活用して売買を実現しています。もっとも、取引は会社側の承認等の枠組みに依拠し、上場市場のようなオープンな板寄せとは異なります。
同マーケットの公開統計(サイト掲載値)では、参加者数・取引成立件数・上場銘柄数などの実績が公表されてきました。これは、未公開株でも一定のセカンダリー需要があり、限定的な場ならば売買は成立することを示しています(具体の数字は同社の最新公表値を要確認)。
4-2. エクイティ・クラウドファンディング発のセカンダリー
日本の株式投資型クラウドファンディング(FUNDINNO、CAMPFIRE Angels、ユニコーン等)は、一次の発行(資金調達)を担ってきました。市場全体は拡大を続けており、研究・調査レポートや企業リリースにも市場規模の推計・動向が示されています。近時は、投資家保護や流動性確保の文脈から、これら一次発行の受け皿で生じた株式の二次流通をどう整備するかが進むテーマです。
4-3. 会社をまたぐ“板”はまだ先
「未上場でもPTSのように多社横断で売買したい」という期待は根強いものの、法制度・投資家保護・フェアディスクロージャー体制の観点でハードルが高く、現状は発行体承認を前提とした個別的な売買が中心です(近年の制度見直しは続いており、流動化を後押しする議論は進行中)。
5. 実務フロー:個人が“中古”で未公開株を手にするまで
- 案件情報の入手
オープン情報は少なく、エクイティCFの投資家コミュニティ、株主コミュニティ、既存株主・創業者からの紹介、専門仲介などが起点。一般公募のような広範な公開勧誘は制度的な制約が大きい。 - 会社の承認取り付け
譲渡制限株式なら取締役会等の承認が必要。ここが最大の関門です。 - 価格交渉とデューディリジェンス(情報開示は限定的)
上場のような継続開示義務はなく、入手できる情報は限定。買い手は**事業・財務・法務(株主間契約や優先株条項)**を最小限でも点検する必要があります。 - 名義書換と対価決済
売買合意後、株主名簿の名義書換が対抗要件。対価は現金が基本。
6. プライシングのむずかしさ:未公開株ならではの“値付け”
- 流動性ディスカウント:いつでも売れない前提の大きな割引。
- 情報非対称性:経営陣・既存投資家が知る情報と外部投資家の情報格差。
- 権利内容の差:優先株/普通株、希薄化条項、ドラッグ/タグ・アロング等の条項次第でバリューは大きく動く。
- 出口想定:M&Aが主流か、TPM→一般市場を視野に置くのかでディスカウント幅が異なる。
上記は理屈としては教科書的ですが、個別案件の交渉力と需給が価格を強く左右します。公開気味の板や約定統計が蓄積しにくいため、相場観が養いづらいのが現実です。
7. 「上場確実」トークにご用心:未公開株は詐欺が多い
金融庁は、未公開株の勧誘トラブルが多発しているとして、「上場予定」と偽った勧誘や架空の発行体などに注意を促しています。「必ず儲かる」「あとで高く買い取る」といった誘い文句は典型的な危険信号。無登録業者リストの公表・注意喚起も継続的に行われています。見知らぬ勧誘は相手の登録有無を必ず確認、不審なら取引を見合わせましょう。
ワンポイント
「未公開株の売買は発行会社または登録を受けた証券会社等に限られる」という基本も、啓発資料で繰り返し強調されています。
8. 個人投資家が取りうる“現実的”な関わり方
8-1. エクイティCFを一次から追い、
株主コミュニティ上の二次流通
を活用
一次募集時に少額から参画し、会社・プラットフォームの投資家向けコミュニケーションを継続的に追う。会社承認の下で行われる限定的なセカンダリー(FUNDINNO MARKET等)にアクセスしやすくなります。
8-2.
TPM上場企業
を“間接的に”研究して一般市場の橋渡しを狙う
TPMはプロ限定で直接買付はできませんが、J-Adviser体制のもと上場準備・開示の整備を進める場として機能。「TPM→一般市場」のステップを志向する会社もあり、将来の公開株として銘柄研究の射程に入れておく価値はあります。
8-3. 情報網をつくる:
発行体・既存投資家・専門家
との接点
未公開株セカンダリーは相対・承認付きが中心。ピッチイベント、地域金融機関、士業・FA、そして投資家コミュニティの縁が案件アクセスの生死を分けます。
9. デューディリジェンス・チェックリスト(簡易版)
- 会社の承認フロー:定款の譲渡制限、承認機関(取締役会/株主総会)、名義書換の段取り。
- 株式の権利内容:優先条項、希薄化条項、ドラッグ/タグ、情報提供義務。
- 資本政策の見通し:次回ラウンドの有無・条件、希薄化リスク。
- 財務の素地:月次のキャッシュバーン、資金繰り、コホート等のユニットエコノミクス。
- 出口仮説:M&Aの確度(業界の買い手マップ)か、TPM→一般市場のロードマップか。
- 適法性の確認:勧誘主体の登録有無、無登録業者の注意喚起リスト照合。
10. いま起きている“新しい流れ”
- オンライン活用の進展:株主コミュニティのオンライン取引化により、案件情報の可視化が前進。セカンダリーの約定データが少しずつ蓄積し始めています。
- 制度面の継続的見直し:未公開株の投資家保護と流動性を両立させる議論が続いており、情報開示や参加者の適格性をテコにした枠組み整備が進展中。将来的により標準化されたセカンダリーが広がる可能性はゼロではありません。
11. まとめ:未公開株の“中古市場”は「点」と「線」で探す
- 自由市場ではない:会社承認を要する譲渡制限が基本。承認・名義書換が売買の要諦。
- プロ限定の取引所はあるが“個人の売買の場”ではない:TOKYO PRO Marketは特定投資家限定。
- 限定コミュニティでの流通は着実に前進:株主コミュニティ×オンラインで点的なセカンダリーが成立。
- 詐欺は常に隣り合わせ:金融庁の注意喚起を繰り返し確認。相手が登録業者か必ずチェック。
結論として、日本の未公開株セカンダリーは「点」と「線」で探す市場です。案件ごとに承認スキームをたどり、コミュニティの線を広げ、制度の潮目を把握して臨む――。地道ですが、それがいまの最短距離です。
※本記事は一般的な情報であり、特定の投資行為を勧誘するものではありません。実際の投資判断・手続は、最新の法令・公表資料・専門家の助言に基づきご対応ください。


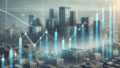
コメント